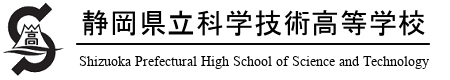Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク
学校の出来事
2学期の終業式が行われました
12月25日(金)2学期の終業式が、コロナウイルス感染防止のため、放送を通じて行われました。
校長先生からお話しいただいた内容の要約を下に記します。
コロナ禍で様々な活動が制限され、多くの全国規模の大会が中止になる中、秋以降、様々な感染症対策がなされ開催された大会の1つ、第100回全国高校ラグビー静岡県大会準決勝での本校ラグビー部の頑張りが印象に残りました。
準決勝の相手は昨年・一昨年と、この大会を連覇している王者、聖光学院です。結果は69対3の完敗でしたが、最後まで戦い抜いた彼らの姿には胸が熱くなりました。この試合で最後まで希望をもつということを考えさせられました。
労働経済学者の玄田有史氏は「希望のつくり方」という著書の中で、希望とは「行動によって何かを実現しようとする気持ち」と述べています。コロナ禍の閉塞感に満ちた世相の中で、あらためて何かを実現しようとする気持ちを持ち続けることが大事であると感じます。希望は実現できない事が多いのですが、そこで努力した人は失望や挫折から学び、新たな希望を得ることが出来るからです。これから皆さんが生き抜く未来を予想するときに、達成できないかも知れない希望に対して挑戦する心、打たれ強い強靱な心身を育むことが、今、皆さんに求められています。
10月から始まった3年生の進路活動では、大きな壁に阻まれている者も少なくありませんが、これまでの努力は次の希望の種です。落ち着いて地道な努力を続け、希望を持ち続けましょう。そのためには、環境も大切です。皆さんを応援してくれる厳しくも暖かい先生方や励まし合う友人が、ふとしたことで支えになってくれるはずです。
1月3日まで1週間ほどの、短い冬休みですが、久しぶりに会う中学時代の友人やいとこなどの緩い結びつきを持つ人達が、希望の作り方の示唆を与えてくれるかも知れません。良いお年をお迎えください。
以上
終業式後の教務課、生徒課、進路課の先生方からのお話を抜粋し以下に記します。
教務課:この1年間何が変わったと感じているか、この先1年間何を変えようと考えていく
か、冬休みにじっくり考え目標を立てて下さい。また軽率な行動をひかえ、新学
期には元気に登校してださい。
生徒課:コロナウイルス感染防止について、基本的な対策を継続してください。交友関係
においては、お互いに思いやる気持ちを持ち接触してください。交通関係では安
全確認をしっかり行い、事故が無いようにしてください。
進路課:8割以上の進路が決定した現在、進路活動の結果を重視するのでなく、取り組み
方やプロセスを重視していく考え方は、今後の人間成長に大きな影響を与えると
思っている。またこのような考え方の最も大切なことは、進路実現に当たって支
えていただいた人たちへの感謝の気持ちを抱くことができることにある。
この話は3年生に向けてのメッセージだが、1,2年生はこのような時期がすぐ
にやってくることを自覚し、今できることに一生懸命に取り組んでください。

12月の表彰者をお知らせします
令和2年度10月中旬から12月までに開催された各種大会等において、校内表彰の対象となった生徒の皆さんの活動成果をお知らせします。なお、本表彰は終業式で行う予定でしたが、全校集会が行われないため、本HPで紹介いたします。
静岡県公立高校PTA連合会善行賞 人命救助 3年 柴田さん
3年 大井さん
3年 望月さん
少林寺拳法部 静岡県新人戦県大会 男子規定組演武 2位 1年 杉山さん
1年 鈴木さん
弓道部 静岡市弓道連盟秋季弓道大会 優勝 2年 高橋さん
第3位 2年 粉間さん
静岡県高等学校中部地区新人弓道大会 男子団体の部 優勝 2年 井柳さん
2年 石部さん
2年 粉間さん
男子個人の部 優勝 2年 井柳さん
第5位 2年 粉間さん
静岡県高等学校新人弓道大会 男子個人の部 第7位 2年 井柳さん
体操部 静岡県新人戦県大会 男子団体 第3位 2年 成岡さん
2年 櫟原さん
2年 寺尾さん
自然科学部 静岡県学生科学賞 県科学教育振興委員会賞 団体 3年 浅谷さん
3年 三宅さん
3年 大石さん
3年 山口さん
個人 2年 宮崎さん
静岡県生徒理科研究発表会県大会 最優秀賞 2年 高林さん
2年 加藤さん
2年 望月さん
図書課 第66回静岡県青少年読書感想文コンクール「高等学校の部」入選 1年 宮本さん
2年 岡村さん
3年 大石さん
3年 才茂さん
建築研究部 星槎道都大学主催 17回高校生住宅設計コンクール 優秀賞 3年 安井さん
国土交通省及び建設産業人材確保・育成推進協議会主催
令和2年度 高校生の作文コンクール 優秀賞 1年 吉田さん
修成建設専門学校主催 第12回修成建築設計競技
日本建築士事務所協会連合会会長賞 2年 沖山さん
星槎道都大学主催 第2回高校生インテリアデザインコンクール
最優秀賞 1年 小澤さん
バドミントン部 令和2年度バドミントン新人大会県大会 学校対抗戦 第3位 2年 中野さん 2年 井上さん
2年 後藤さん
2年 川嶋さん
2年 北沢さん
2年 田村さん
1年 永野さん
家庭科 静岡県中部農林事務所主催 高校生による和の給食コンテスト
審査員奨励賞 3年 岩城さん
3年 紅林さん
3年 狩谷さん
令和2年度静岡県高等学校新人大会 なぎなた競技 男子個人試合の部
第3位 1年 中澤さん
以上
選挙に関する出前授業が行われました
12月21日(月)LHRの時間、高等学校における主権者教育として、2年生を対象に選挙に関する出前授業が行われました。講師は静岡市葵区選挙管理委員会事務局および静岡市議会事務局調査法制課の職員の方にお願いしました。
内容は、まず葵区選挙管理委員会事務局の方から、選挙に関する歴史。投票をする意義。年齢別投票率や投票者数の現状。候補者選択の際の情報収集方法。投票所入場券の見方。投票所での実際の投票方法と注意事項。選挙運動に関する禁止事項等について、お話しいただきました。
次に静岡市議会事務局の方から、市長と市議会と市民との関係や各々の役割について。静岡市議会の概要(議員数、男女比、定例会・臨時会・常任委員会等の会議体、活動内容等)について紹介がありました。
最後に生徒代表によるお礼の言葉をもって終了となりました。
今回の出前授業により、自分達の世代向けの政策を実現するには、投票に行くことが重要であることが理解できたと思います。来年度は県知事選挙、衆議院総選挙が予定されており、有権者となる生徒が出てきます。有権者となったらぜひ投票所に向い一票を投じてほしいと思います。


生徒会の正副会長選挙が行われました
12月18日(金)次期生徒会の正副会長選挙が行われました。今回の選挙はコロナウイルス感染防止のため、立会演説会と投票共に各クラスで行われました。
立会演説会では、会長立候補者1名、副会長立候補者2名に対する応援演説と立候補者により事前録画された演説動画が流されました。立会演説終了後、投票上の注意が放送され、各クラスにて投票が行われました。
今回の選挙は正副会長の立候補者が定数のため信任投票となりました。
投票の結果候補者は各々信任され、会長の鹿内さん、副会長の河村さん、伊東さんの3名が次期生徒会を担っていくことになりました。
信任された新生徒会長・副会長は立会演説会で訴えたことの実現を目指し、活躍されることを期待しています。
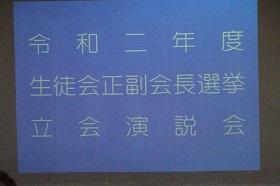
1年生の学年集会が行われました
12月11日(金)のLHR、1年生は学年集会が行われました。
最初に、11月13日(金)のLHRの時間に行われた学年体育大会3種目と総合順位の上位3チーム(下記参照)に対する表彰式が行われました。
競技種目 1位 2位 3位
①ロープジャンプEX 物質工学科 都市基盤工学科 13HR
②八の字タイムアタック 建築デザイン科 物質工学科 13HR
③クラス対抗リレー 建築デザイン科 都市基盤工学科 14HR
総合順位 優勝:建築デザイン科 2位:都市基盤工学科 3位:物質工学科
続いて学年主任の先生から、県内の高校1年生6,000人と県内事業所で働く労働者約1,000人に実施された「高等学校に関するニーズ調査」結果において、同じ質問に対する高校生と労働者のニーズの差異について紹介がありました。この調査結果は、これから社会に出るにあたり、どんなことが求められているかを考えるきっかけになり、今回の学年集会の目的である「自分の進路に向き合うきっかけを作る」につながることと思う。との話がありました。
最後に教務課より2学期の成績処理について。進路課より今年の進路活動の状況について。生徒課よりスマートフォンの利用に関する注意事項について。学習時間調査係より第3回定期試験前9日間の学習時間調査結果について、話がありました。
今年度の学習期間も残り約10週、2年生への進級を見据え、今一度学習への取り組みを含む生活習慣の見直しが望まれます。