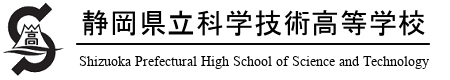Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク
学校の出来事
ジャパンマイコンカーラリー2020全国大会
1月11日(土)、1月12日(日)に北九州市小倉でジャパンマイコンカーラリー全国大会2020が開催されました。
電子工学科の3年生7名がベーシッククラス、カメラクラスに出場しました。
生徒は課題研究、放課後を用いてマイコンカーの製作、プログラムの調整を行ってきました。
その研究の成果を全国大会でも発揮することができました。
記録
ベーシッククラス
予選1回目 コースアウト
予選2回目 28.04秒
カメラクラス
1回目 コースアウト
2回目 65.08秒
ベーシッククラス :総合19位(参加台数50台・完走率 56.0%)
カメラクラス :総合6位 (参加台数20台・完走率 35.0%)
ベーシッククラスでは、決勝トーナメント出場の16枠には1歩足らず入ることができませんでした。カメラクラスは、初めての全国大会の出場となりましたが、総合6位と好成績を収めることができました。
各クラスとも自分たちでマイコンカーを製作し、プログラムを試行錯誤したマイコンカーが完走する姿を見て達成感を得ていました。
国家資格「2級土木施工管理技術検定試験(学科)」の合格率が、全国平均の1.6倍!!
このほど、昨年10月に行われた国家資格「2級土木施工管理技術検定試験(学科)」の合格発表があり、受験した本校2年生36名(部活動の大会等で受験できなかった者を除く)のうち33名が合格しました。
合格率は91.7%で、全国平均の1.6倍
(全国平均合格率は、大学生や社会人を含めて56.6%)
多くの工業高校では、専門学習の集大成として3年生が受験する資格試験ですが、本校都市基盤工学科では、構造物を造るために必要な知識のため、2年次に「2級土木施工管理技術検定試験(学科)」を、都市の美観を考える知識を身につけるため、3年次に「2級造園施工管理技術検定試験(学科)」の合格を目指す指導を行っています。
今回の合格は、その良い励みになったと思います。
☆ 建築デザイン科 球技大会 ☆
1月10日(金)LHRの時間、建築デザイン科は恒例の学年対抗球技大会を開催しました。
企画運営からすべて生徒が行い、開会宣言・ルール説明の後、バスケットボール・ドッジボール・ピンポン玉リレーの3種目で競技しました。
クラスTシャツを着て結束を高め、楽しく身体を動かしながら親睦を深めることができました。
成績は、優勝3年生、準優勝2年生、第3位1年生となりました。
★手帳甲子園中部大会出場の物質工学科・坂本さんがラジオ出演します★
昨年12月に名古屋市で行われた「NOLTYプランナーズ主催 第8回手帳甲子園」の中部大会(静岡・愛知・岐阜・
三重・富山・福井・石川・長野)に出場した本校物質工学科2年・坂本さんが、1月11日(土)20時から
SBSラジオで放送予定の「鬼頭理枝のテキトーナイト!!!」に出演することになりました。
「手帳甲子園」の出場逸話などが聞けることと思います。
放送は生放送で、坂本さんの出演時間帯は20時20分頃からの「TNN学校ニュースステーション ご意見番!
鬼頭里枝です!」コーナーの予定です。
是非皆様、ラジオを聞いていただければと思います。 SBSラジオ 鬼頭理枝のテキトーナイトHP
☆都市基盤工学科 課題研究 防災班が出前講座を受講☆
1月7日(火)、都市基盤工学科3年生「課題研究」の授業で、防災関係に取り組む班の生徒たちが、災害の防止や危機管理を担う「一般社団法人中部地域づくり協会」(名古屋市)による出前講座を受講しました。
頻発する激甚災害の状況を、過去の事例やデータ、映像などで説明していただき、その恐ろしさについて学ぶことができました。また、VRの機器を装着してリアルに体感することにより、命を守る行動の重要性をあらためて実感しました。
今回の出前講座で、日頃学習して取り組んでいることの重要性を再認識することができました。
【生徒の感想から】
「高校生ができる役割とは何か、災害から命を守ることの大切さ ”1分1秒”が生死を分ける。今日の講座であらためて都市基盤工学科の大切さ、その役割を認識できました。自分のため、人のため、社会のために今日学んだことを活かしていきたいと思いました。」
犬飼所長の講義 「過去から学ぶ」
VR体験
実際に来たら、もうそこで終わってしまうこともある。
この体験こそ貴重な事。
3学期の始業式と生徒会任命式が行われました
1月6日(月)、3学期の始業式と生徒会任命式が行われました。
始業式では、校長先生から「『運』について、運気を引き寄せるには」ということについて、田坂広志先生の著書「運気を磨く」という本を紹介しながら、次のようなお話をいただきました。
運気を引き寄せるには、自分の気の持ちよう、常に前向きな姿勢で外に向かってエネルギーを発信する人ほどうまく人生が回っていき、プラス方向に成果が出ていく。外に向かってエネルギーを発信するためには、成功体験を積み上げていくことによって得られる自己肯定感をもつこと。いずれにしても、日頃の心がけが運気を引き寄せることになる。一日一日を有意義に過ごしてほしい。
始業式終了後、生徒会任命式が行われ、昨年12月18日(水)の投票により決定した正・副生徒会長3名に校長先生から辞令が交付されました。続いて新生徒会長から、「令和としてふさわしい生徒会を作っていきます」との挨拶がありました。

ロボット工学科~師走~
ロボット工学科~師走~
三明機工コラボレーション授業
12月17日(火) ロボット工学科3年生12名が、三明機工株式会社でコラボレーション授業を行いました。
作業の安全に関する注意事項を聞き、バーチャルロボットセンターで説明を受けました。このロボットセンターは、工場のロボットの動作やラインの配置など大型の画面で事前に確認をすることができ、システム作りにとても活躍が期待されるものです。説明後、実機による実技指導を受け、ロボットにティーチングし操作を行いました。


ロボットアイデア甲子園2019全国大会
12月21日(土)国際ロボット展が開かれた東京ビッグサイトにて、ロボットアイデア甲子園2019全国大会(FA・ロボットインテグレータ協会主催)が開催されました。全国8地区から11名の代表者が集まり、6分間のプレゼンテーションを行い、産業用ロボットのアイデアを競い合いました。
本校からはロボット工学科2年 佐藤 亘さん 「Dream Barber 382」が出場しました。
当日は、ロボット研究部とロボット工学科有志も会場入りし、応援、国際ロボット展を見学しました。




★令和元年度 工業科・理数科課題研究発表会のお知らせ★
工業科3年生および理数科2年生対象に、週3時間の授業で取り組んできた「課題研究」の発表会を開催します。
日々の研究成果を指導者や仲間そして後輩たちに発表するもので、工業科は3年間、理数科は2年間の学習の
総まとめと位置付けられています。各学科、下記の予定で実施します。
工業科は新学期早々、ご家庭に案内文書を配布します。参加を希望される場合は、申込書をクラス担任にご提出
くださいますようお願いいたします。なお理数科につきましては、詳細を後日ご案内します。
課題研究発表会の開催日時と教室等 ※教室の詳細は後日配布される案内をご参照ください。
機械工学科 1/23木 14:10-16:00 視聴覚室
電気工学科 1/29水 10:35-12:25 電気工事室
ロボット工学科 1/30木 14:10-16:00 視聴覚室
電子工学科 1/30木 14:10-16:00 第1,2,3会議室
情報システム科 1/27月 10:35-12:25 アプリケーション実習室
建築デザイン科 1/30木 14:10-16:00 建築デザイン科製図室
都市基盤工学科 1/28火 13:10-15:00 視聴覚室
物質工学科 1/27月 10:35-14:00 視聴覚室
理数科(理工科 ※2年生) 2/17月 13:10-16:00 視聴覚室
★写真は昨年度の課題研究発表会です。
2学期の終業式と表彰が行われました
12月23日(月)、2学期終業式と表彰式が行われました。
終業式では、校長先生から次のような式辞をいただきました。
「2学期の終業式の本日は、1年間を締めくくる節目の日。節目は1年間を振り返り、次につなげる機会である。1年間を振り返り、どんなことを頑張ったかその成果を確認し、それに満足せずに次につなげる『NEXT ONE』を考える冬休みとしてほしい。来年新たな目標を胸に、目を輝かしてこの場に集うことを期待しています。」
終業式に続いて、5団体及び28名の表彰が行われました。
表彰内容を以下に記します。
物質工学科 高校生による和の給食コンテスト 審査員奨励賞
美術部 第8回静岡県モノづくり競技大会ポスター募集 優秀賞
第25回RADデザイングランプリ 奨励賞
入選2件
令和元年度静岡県高等学校総合文化祭美術・工芸部門 第35回中部展 7件
建築研究部 愛知産業大学主催 第17回建築コンペティション A部門 優秀賞
第18回建築コンペティション B部門 優秀賞
第19回建築コンペティション C部門 最優秀賞
福山大学建築学科主催 高校生デザインコンペ2019 優秀賞
長崎総合科学大学主催 第22回全国高校生設計アイデアコンテスト 優秀賞
電子工学科 ジャパンマイコンカーラリー2020 東海地区大会 Basic Class
5位 6位 8位 9位
Camera Class
1位 3位
図書課 静岡県高等学校読書感想文コンクール 入選 4件
総務課 県高P連高校生善行表彰 善行賞(救命活動) 2件
弓道部 静岡県高等学校新人弓道大会 4位
ロボット研究部 静岡県高校生ロボット競技大会 自律制御ロボット部門 3位
自然科学部 静岡県生徒理科研究発表会 県大会 高文連会長賞
物質工学科 第8回手帳甲子園中部大会 優秀賞


★第8回手帳甲子園中部大会に物質工学科2年・坂本さんが出場しました★
先般、このホームページでもお伝えしたとおり、12月21日(土)に愛知県名古屋市・学校法人名古屋大原学園
4号館で行われた㈱NOLTYプランナーズ主催の「第8回手帳甲子園中部大会」に、本校物質工学科2年の坂本さんが
出場しました。中部大会には、静岡・三重・岐阜・愛知・富山・石川・福井・長野各県の範囲から選ばれた5名が
出場し、手帳の活用法についてプレゼンテーションしました。
本校の坂本さんは、静岡県代表として大観衆の注目の中、立派に自分の手帳活用法を発表しました。
結果は惜しくも優秀賞で、東京での全国大会出場権を得られる最優秀賞を逃してしまいましたが、十分に学校代表・
そして静岡県代表としての重責を果たしたと思います。

23日の本校2学期終業式で優秀賞の校内表彰を行いました。